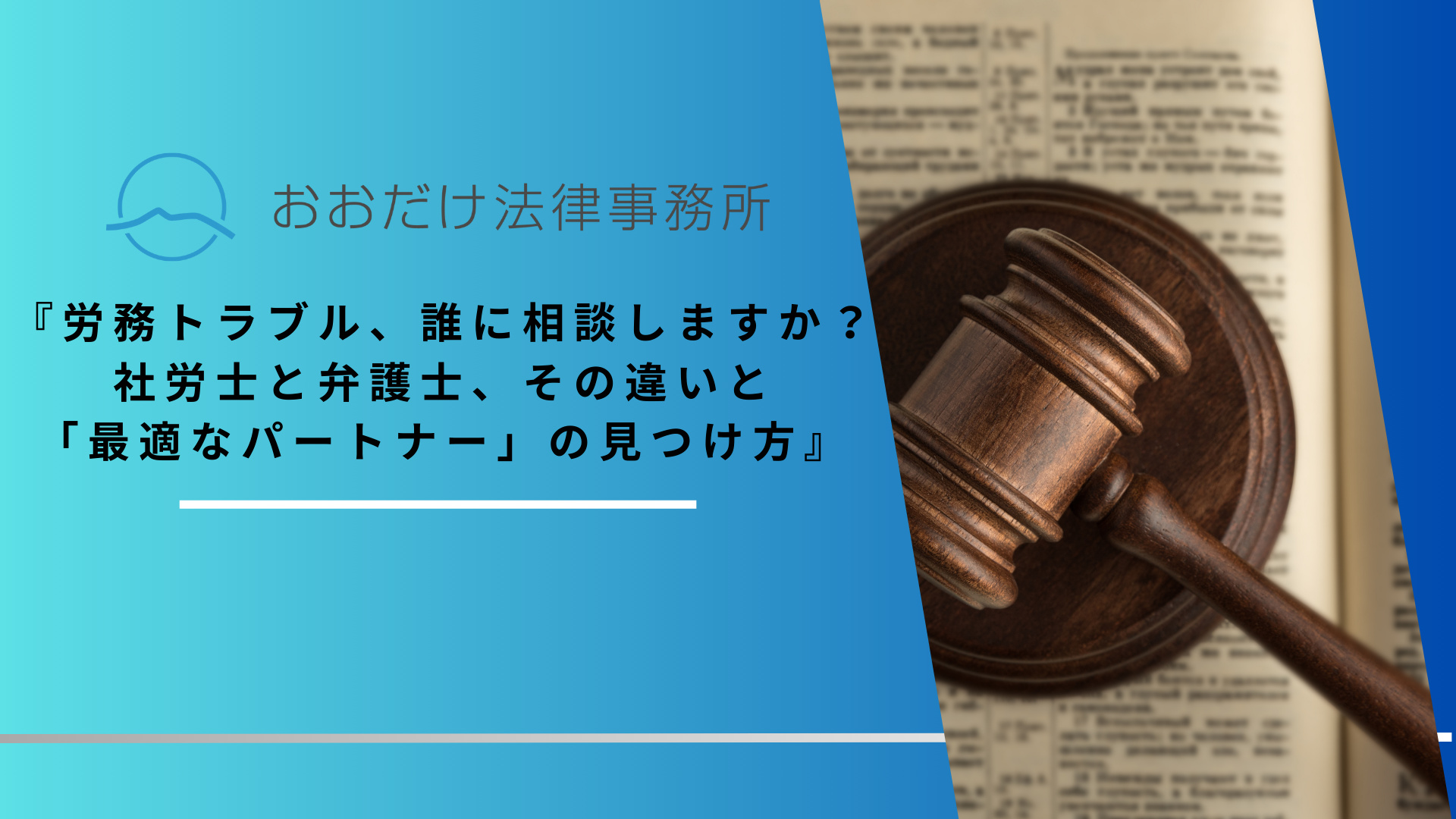
「従業員から突然、未払い残業代を請求する内容証明郵便が届いた…」
「退職した社員との間で、解雇をめぐってトラブルになっている…」
企業の成長を目指す中で、人事労務に関する悩みやトラブルは避けて通れない課題です。経営者や労務担当者の方であれば、このような「ヒヤリ」とする場面に一度は遭遇したことがあるかもしれません。
こうした労務問題の相談先として「社会保険労務士(社労士)」と「弁護士」が思い浮かびますが、両者の役割の違いを正確にご存知でしょうか。実は、相談するタイミングや内容に応じて、それぞれの専門家が持つ強みは異なります。
相談相手の選択は、問題解決のスピードと質を大きく左右します。
本コラムでは、社労士と弁護士の役割の違いを分かりやすく解説し、企業の成長を支える最適なパートナーを見つけるためのヒントをお伝えします。
平時の労務管理を支えるパートナー「社会保険労務士(社労士)」
社会保険労務士(社労士)は、企業の「人」に関する手続きや、労務管理を専門とする国家資格者です。その役割は、会社が法律に則った健全な運営を続けるための「日々の適正な労務管理」を構築・維持する、企業にとって非常に身近なパートナーと言えるでしょう。
社労士の主な業務
労働・社会保険の手続き代行
従業員の入退社に伴う雇用保険や社会保険の資格取得・喪失手続き、年度更新など、複雑で専門的な行政手続きを代行します。
帳簿書類の作成
労働者名簿や賃金台帳といった、法律で義務付けられている帳簿を作成します。
就業規則の作成・見直し
会社のルールブックである就業規則の作成や、法改正に合わせた見直しを行います。
労務相談・指導
日々の勤怠管理や従業員との円滑なコミュニケーション、働きやすい職場環境づくりに関する相談に応じ、専門的な指導を行います。
助成金の申請サポート
雇用関係の助成金について情報提供し、申請をサポートします。
このように、社労士は主に「紛争が起こる前の」平時における、適正な労務管理の構築と円滑な事業運営を支える専門家です。
法的紛争の解決を担う専門家「弁護士」
弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができる法律の専門家です。その業務範囲は非常に広く、企業の法務戦略から個人の相続問題まで多岐にわたりますが、労務分野における最大の強みは、「紛争」を解決する力にあります。社労士が主に平時の労務管理を支えるのに対し、弁護士は問題が法的な紛争に発展した際に、その解決を担う専門家です。
労務分野における弁護士の主な業務
交渉の代理
従業員との間で発生したトラブル(解雇、残業代、ハラスメント等)について、会社側の代理人として相手方と直接交渉します。
労働審判・訴訟の代理
紛争が労働審判や裁判に発展した場合、代理人として法廷に立ち、会社の正当性を主張・立証します。
法的効力を持つ書面の作成
交渉がまとまった際の合意書や、将来のトラブルを防ぐための各種契約書など、法的に有効な書面を作成します。
弁護士は、問題がこじれてしまった際に、法律に基づいた最終的な解決を目指すプロフェッショナルです。
決定的な違いは「紛争」への対応力
両者の専門性を見た上で、その決定的な違いをまとめると「法的な紛争に発展した際の代理権の有無」と言えます。
近年では、研修を受け試験に合格した「特定社労士」であれば、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、個別の労働紛争の解決(あっせん等)に携わることができます。しかし、この手続きには強制力がなく、相手方が交渉に応じなければ解決には至りません。そして、もし話がまとまらず労働審判や訴訟に移行した場合、社労士が会社の代理人になることは法律上できません。
そのため、「まずは顧問の社労士に相談したが、事態が深刻化し、『ここからは弁護士の領域です』と言われて、慌てて弁護士を探すことになった」というケースは少なくありません。これは、解決までの時間が長引くだけでなく、専門家を探す手間や費用も二重にかかってしまう可能性があります。
|
業務内容 |
社会保険労務士 |
弁護士 |
|
日常の労務相談 |
◎ |
〇 |
|
社会保険・労働保険の手続き |
◎ |
△ |
|
就業規則の作成 |
◎ |
◎ |
|
助成金申請 |
◎ |
△(専門外) |
|
紛争時の代理交渉 |
△(ADR等の一部のみ) |
◎ |
|
労働審判・訴訟の代理 |
× |
◎ |
「社労士資格を持つ弁護士」という最適な選択肢
では、企業にとって最も頼りになるパートナーは誰なのでしょうか。
ここで強調したいのは、どちらの専門家が優れているか、ということではありません。弁護士は法律のプロですが、必ずしも人事労務の細かな実務手続きや最新の助成金情報に精通しているとは限りません。一方で、社労士は手続きや平時の労務管理のエキスパートですが、法廷での紛争解決はできません。
そこでご提案したいのが、「社労士の資格を併せ持つ弁護士」をパートナーにするという選択です。これには、他にはない大きなメリットがあります。
真のワンストップサービス
日常のちょっとした労務相談や社会保険の手続きといった「平時」のサポートから、万が一の労働審判や訴訟といった「有事」の対応まで、すべて一つの窓口で完結します。担当者が変わることで生じる情報の引き継ぎ漏れや、改めて専門家を探す時間とコストをなくし、あらゆるフェーズで迅速かつ的確な対応が可能です。
「紛争」を見据えた、質の高い「予防法務」
これが最大の強みです。弁護士として「裁判になったらどう判断されるか」という紛争の最終局面を知っているからこそ、平時の就業規則作成や労務管理の段階で、将来の法的リスクを徹底的に洗い出し、未然に防ぐご提案ができます。例えば、就業規則の条文一つをとっても、「手続き上、適法か」という社労士の視点に加え、「万が一の際に、裁判で会社を守る武器となるか」という弁護士の視点を融合させた、より強固なものを作成できるのです。
「守り」と「攻め」の両面サポート
助成金の活用や働きやすい職場環境づくりといった、企業の成長を後押しする「攻め」の労務管理(社労士の視点)。そして、法改正への対応や労務トラブルから会社を「守る」法務(弁護士の視点)。この両方を、企業の状況を深く理解した一人の専門家が、経営に寄り添いながらバランスよく提供できることも、大きなメリットです。
【まとめ】企業の成長ステージに寄り添うパートナーとして
人事労務の問題は、企業の成長を左右する非常に重要な経営課題です。
問題が起こってから対処する「事後対応」ではなく、日頃から会社の状況を深く理解し、予防から有事まで一貫して任せられる専門家がいることは、経営者にとって何よりの安心材料となるはずです。
当事務所には、社会保険労務士の資格を持つ弁護士が在籍しております。
手続きのことから、万が一のトラブルまで、どのような些細なことでも構いません。人事労務のことでお悩みの際は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。貴社の持続的な成長を、法務と労務の両面から力強くサポートいたします。