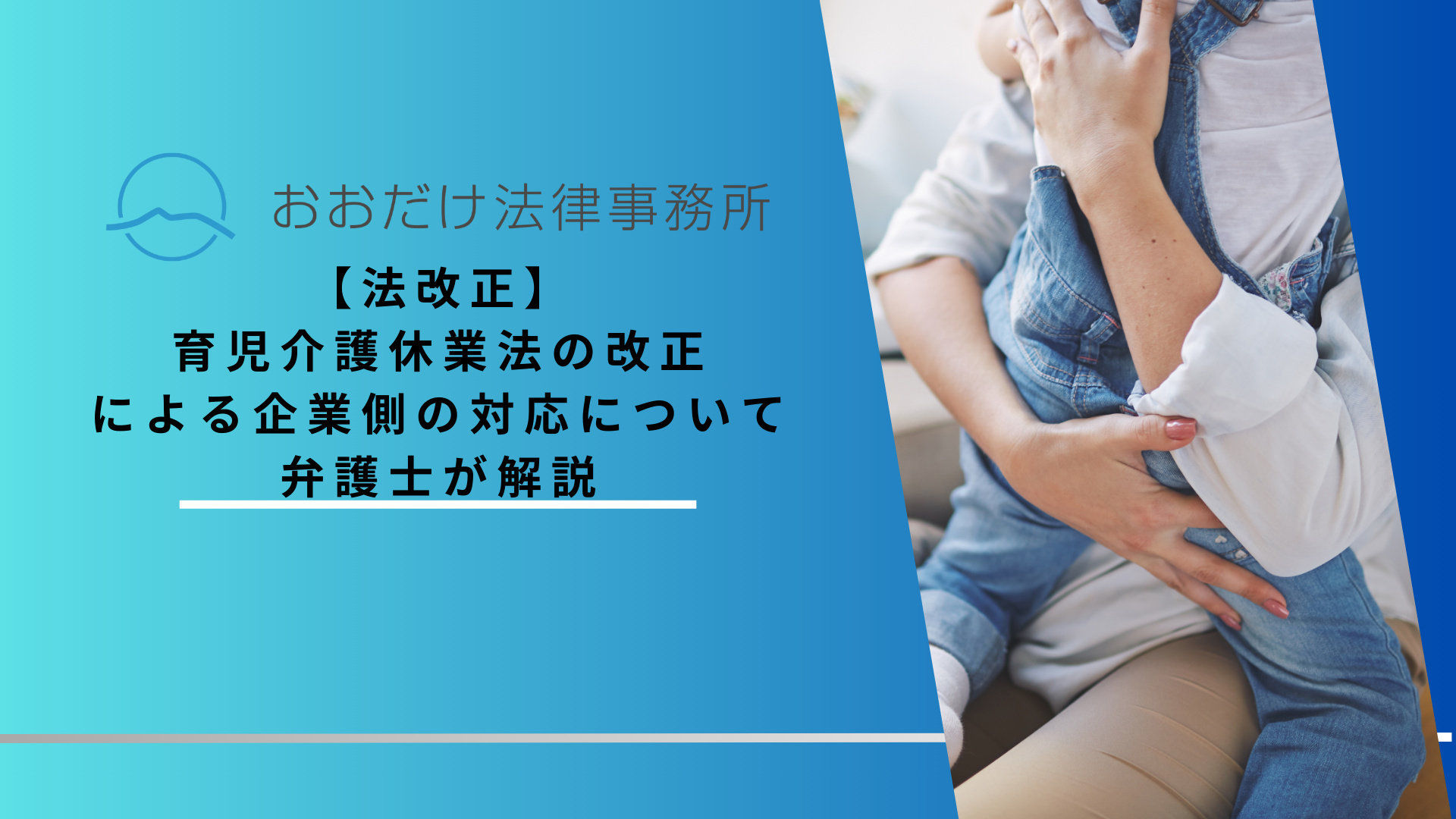
2025年4月・10月より育児・介護休業法が大きく変わります!就業規則の改定準備は万全ですか?
2025年4月1日と10月1日、仕事と育児や介護の両立を一層支援するための改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。今回の改正は、従業員の働き方の柔軟性を高め、介護による離職を防ぐことを目的とした重要なものであり、多くの企業で就業規則の見直しが必須となります。
法令遵守はもちろんのこと、従業員が安心して働き続けられる環境を整備するために、以下の改正ポイントをご確認いただき、早期の対応準備をお願いいたします。
主な改正点の概要
今回の法改正は、2025年4月1日と10月1日の二段階で施行されます。
特に事業主に新たな「義務」が課される項目が多く含まれています。
【2025年4月1日施行の主な改正点】
子の看護休暇が「子の看護等休暇」へ拡充されます
対象年齢の拡大
対象となる子の範囲が、現行の「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に引き上げられます。
取得理由の追加
病気やけがなどに加え、「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園・入学式、卒園式」への出席も取得理由として認められます。
除外規定の廃止
労使協定による「勤続6か月未満」の従業員を対象外とする規定が廃止されます。
【企業の対応】
名称変更、対象者・取得事由の拡大に伴う就業規則の改定が必須です。
残業免除(所定外労働の制限)の対象者が拡大されます
対象年齢の拡大
3歳未満の子を養育する従業員が対象でしたが、これが「小学校就学前の子」を養育する従業員まで**拡大されます。
【企業の対応】
就業規則の改定が必須です。
介護離職防止のための措置が強化されます(義務化)
雇用環境の整備(義務)
事業主は、介護に直面した従業員が各種制度を円滑に利用できるよう、「研修の実施」「相談窓口の設置」「社内事例の提供」「方針の周知」のうち、いずれか1つ以上の措置を講じなければなりません。
個別周知・意向確認(義務)
従業員本人や家族の介護に直面した旨の申し出があった場合、事業主は個別に介護休業制度などを周知し、取得意向を確認することが義務となります。また、40歳に達する従業員等への事前の情報提供も義務化されます。
育児休業取得率の公表義務が拡大されます
対象企業の拡大
男性の育休取得率等の公表義務が、現行の「従業員1,000人超」の企業から、「従業員300人超」の企業まで拡大されます。
【2025年10月1日施行の主な改正点】
3歳から小学校就学前の子のための「柔軟な働き方」の選択肢導入が義務化されます
事業主の義務
事業主は、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して制度を導入し、従業員がその中から1つを選んで利用できるようにしなければなりません。
✅始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制など)
✅テレワーク
✅保育施設の設置運営やベビーシッター費用の補助など
✅新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
✅短時間勤務制度
【企業の対応】
措置の選択、労使での意見聴取、そして就業規則への明記が必須となります。
個別の意向聴取と配慮が義務化されます
意向聴取(義務)
従業員から妊娠・出産の申し出があった時と、子が3歳になる前の適切な時期に、勤務時間や場所、業務内容など仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取しなければなりません。
配慮(義務)
聴取した意向に対し、事業主は状況に応じて配慮することが求められます。
就業規則の見直しは急務です
ご覧いただいた通り、今回の法改正は多岐にわたり、特に「義務」とされる項目への対応は待ったなしの状況です。2025年4月1日施行の改正内容については対応済みでしょうか。また、10月1日施行の改正内容についてはいかがでしょうか。自社の制度を確認し、計画的に就業規則の改定作業を進めることを強くお勧めします。
当事務所電話は、今回の改正へ対応した就業規則の改定はもちろん、円滑な法対応と、より良い職場環境の実現に向けたお手伝いが可能です。お気軽にご相談下さい。