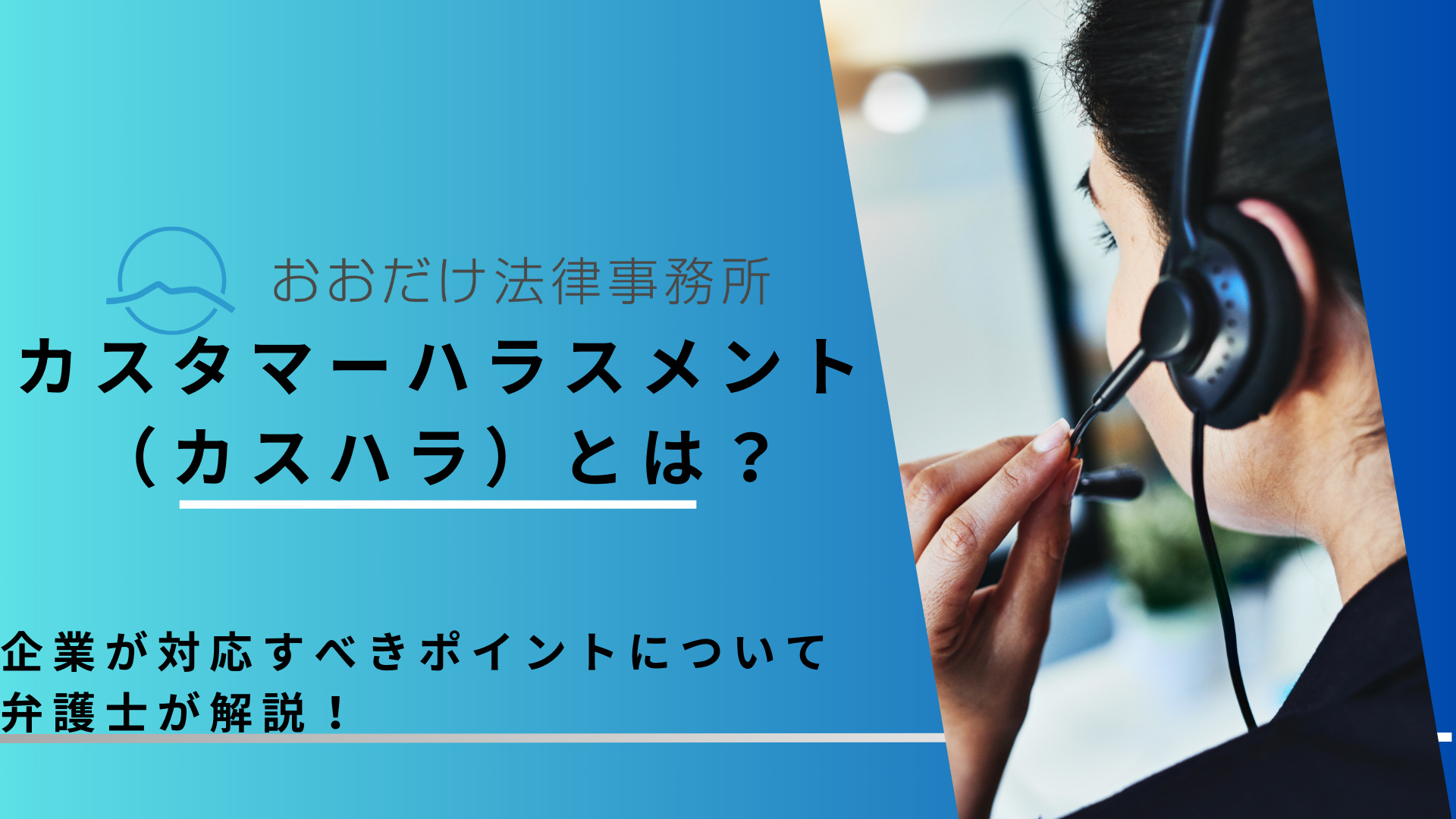
-
目次
カスタマーハラスメント防止条例(東京都)とは?
東京都は、2024年10月4日に「カスタマーハラスメント防止条例」(以下、カスハラ防止条例)を全国で初めて可決しました。当該条例は、2025年4月1日から施行される予定です。
この条例は、顧客等から従業員に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものをカスタマーハラスメントとし、カスタマーハラスメントを防止し、顧客等の豊かな消費生活、就業者の安全及び健康の確保、事業者の安定した事業活動を実現し、公正で持続可能な社会の形成を促進することを目的としています。
-
カスタマーハラスメント(カスハラ)の定義と、当てはまる具体的な行為
前述のとおり、防止条例では、カスタマーハラスメントは、顧客等から従業員に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものとされています。
そして、「著しい迷惑行為」とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為とされています。例えば、以下のような事例が該当します。
違法な行為
→暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去 他
不当な行為
→申出の内容又は行為の手段・態様が社会通念上相当であると認められないもの
代表的な行為の類型として、申出の内容が相当と認められない場合の例
事業者の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
事業者の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
行為の手段・態様が社会通念上相当と認められない場合の例
→身体的な攻撃、精神的な攻撃、威圧的な言動、土下座の要求、執拗な言動、拘束的な行動、差別的な言動、性的な言動、従業員個人への攻撃等
違法な行為は刑法の構成要件に該当する、要するに犯罪ですから、これがカスハラにあたると判断することは容易でしょう。
不当な行為については、正当なクレームなのか、カスハラと断じて対応するのか、線引きに迷うケースもあろうと思います。
特に、「精神的な攻撃」「威圧的な言動」「執拗な言動」といったあたりは判断が難しいのではないかと思います。可能であれば、社内で事例を積み上げ、その検討結果を社内で共有し、共通の判断基準を持つことができたら良いかと思います。
-
カスハラ防止条例の基本理念
カスハラ防止条例は、基本理念として、カスハラが就業者の人格又は尊厳を侵害し、就業者の就業環境を害するとともに、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであると断じ、社会全体でカスハラの防止を図る必要がある、としています。
このような基本理念から、東京都は、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない。」とし、カスハラの禁止を明示しています。
また、当該条例では、都ではカスハラ防止指針を策定し、事業者は、指針に基づき、必要な体制の整備や被害あった者への配慮、マニュアルの作成その他必要な措置を講じるよう求めています。
-
企業に求められるカスハラ対応
カスハラ防止条例では、企業がカスハラを防止するために積極的に取り組む責任が定められています。具体的な対策として、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」では、以下のようなことが示されています。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談先(上司、職場内の担当者)をあらかじめ定め、これを就業者に周知する
相談を受けた者が、あらかじめ定めた留意点などを記載したマニュアルに基づき対応する 等
カスタマーハラスメントを受けた就業者への配慮のための取組
事案に応じ、カスタマーハラスメント行為者に複数人で対応することやメンタルヘルス不調への相談対応 等
カスタマーハラスメントを防止するための取組
カスタマーハラスメント行為への対応に関するマニュアルの作成や研修を行う 等
取引先と接するに当たっての対応
立場の弱い取引先等に無理な要求をしない、取引先の就業者への言動にも注意を払う
自社の社員が取引先でカスタマーハラスメント行為を疑われ、事実確認等を求められた場合は協力する 等
厚労省ではすでに「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」というものが作成されていました。東京都の前記「基本的な考え方」においても、当該マニュアルに沿って内容を検討するとされておりますので、今後示される具体的な措置の詳細は、当該マニュアルに記載されたものと内容を大きく異にするものではないだろうと思われます。
-
カスハラへの適切な対応を怠った場合の企業リスク
カスハラ防止条例が制定されたというのは、カスハラに対して適切に対応すべき、という世の中の考え方の変化が背景にあります。適切に対応しなかった場合、企業は以下のようなリスクを負う可能性があります。カスハラ防止条例の違反に罰則はありませんが、以下のようなリスクを考えると、適切な対応を行うことが望ましいでしょう。
従業員の離職リスク
カスハラに適切に対応しないと、従業員が精神的に疲弊し、最終的には休職や離職に繋がる可能性があります。
企業の信用低下
従業員がカスハラに苦しむ姿を見た他の従業員や顧客の士気が低下し、企業のブランドや信用に悪影響を与える恐れがあります。
法的リスク
労働契約においては、事業主は従業員の就業につき、安全に配慮する義務があるとされています。カスハラ対応を怠り、これによって従業員が精神的に病んでしまった、というような事態に発展した場合、事業主たる企業は、従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。
-
カスハラに関するお悩みは当事務所にご相談ください
東京都カスタマーハラスメント防止条例の制定・施行に伴い、企業はカスハラ防止に向けた積極的な対応が求められています。
顧客との適切な関係を保ち、従業員の安全を確保するために、企業は体制整備や研修、マニュアル作成を進める必要があります。厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が参考になります。
また、弁護士は、実際にカスタマーハラスメント事案が発生した場合の対加害者対応や被害に遭った従業員への対応に関するアドバイス、今後示される指針に従った体制づくりへのアドバイスなど、効果的なカスハラ対策のお手伝いをすることが可能です。お気軽にご相談下さい。